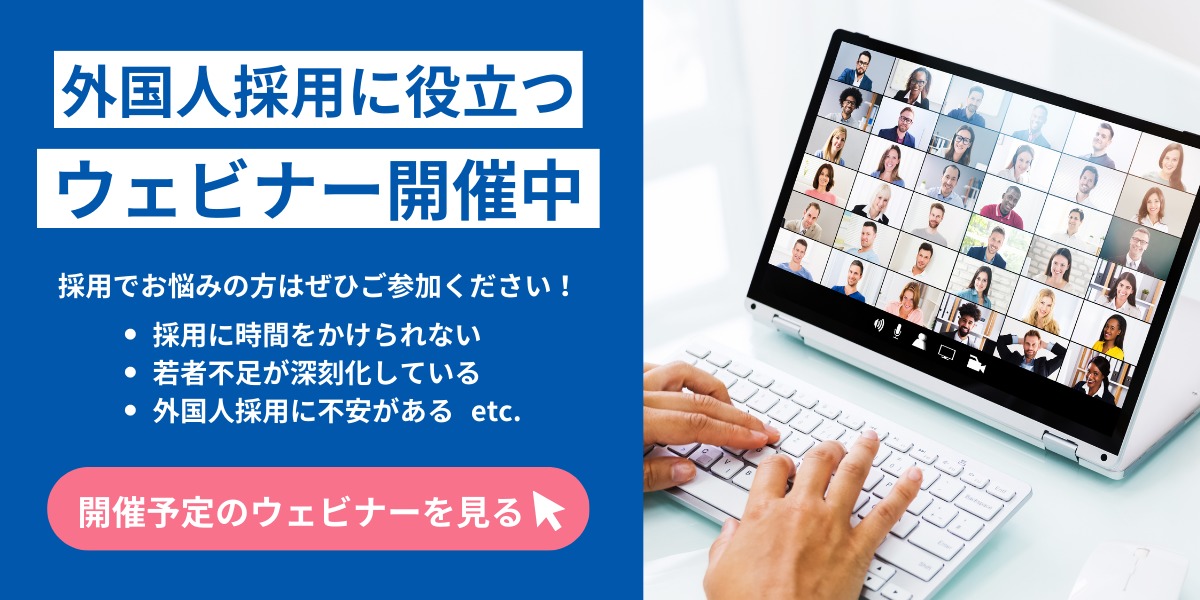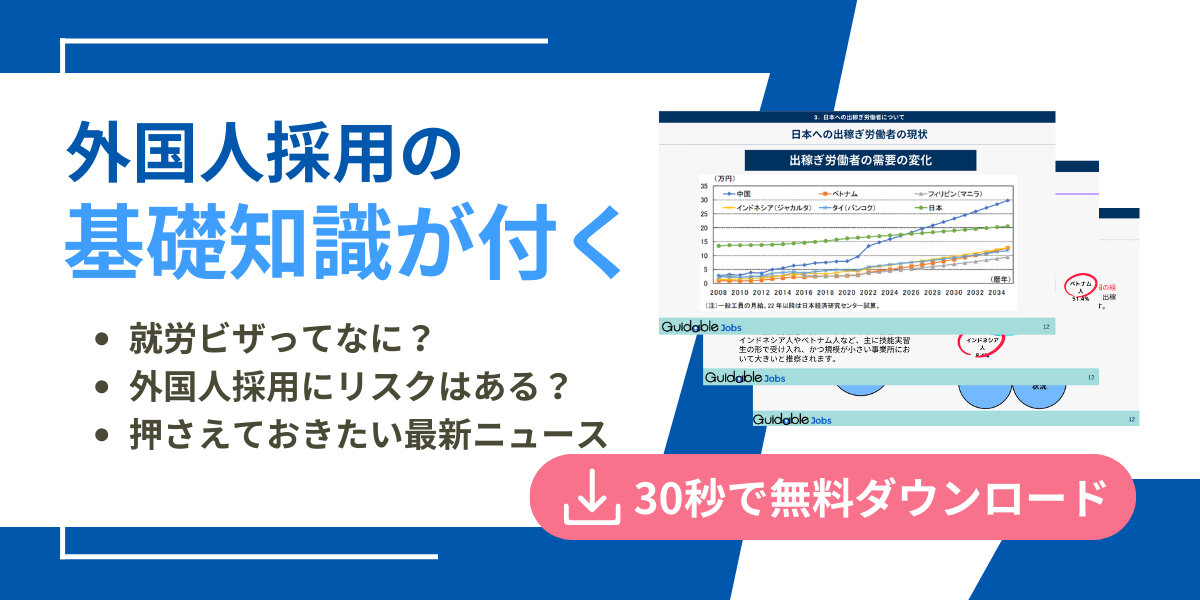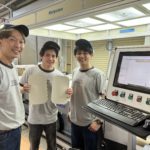外国人雇用での悩み、困りごと5選とその解決策は?

企業のグローバル化や人材不足の対策などを理由に、近年は外国人を雇用する企業が増えています。
日本政府による「外国人雇用の受け入れ」に関する新たな政策も施行され、今後さらに外国人雇用が増加していくことが予想されています。
しかし外国人を雇用している企業のあいだでは、さまざまな困りごとがあるのも事実。そこで今回は、外国人を雇用する際の困りごと5選と、その対策法について解説します。
目次
外国人雇用は増えている?
厚生労働省が発表した統計によると、2022年10月末で日本国内の「外国人労働者は182万人で過去最高を更新しています。
2012年は68万人でしたので、この10年で100万人以上も増えていることになります。
現在、政府は外国人の受け入れに関する新たな政策を発表し、外国人労働者の雇用を推進しています。
2023年4月の有効求人倍率は、建設業界では約4倍と高水準で、今後はさまざまな業界でますます人材が足りなくなると考えられています。
外国人雇用の困りごと(トラブル・問題)で多いものは?
外国人を雇用する際、どのような困りごとがあるのでしょうか。
具体的に解説していきます!
1.日本語でのコミュニケーションがとれない

雇用した外国人は日本語能力がまちまちで、スムーズにコミュニケーションがとれないケースもあります。
この問題の背景として、日本語試験の評価基準があげられます。
外国人は「日本語能力試験(JLPT)」で一定のレベルに合格することによって、自分に日本語能力があることをアピールして企業に入ります。
しかし日本語能力試験は、言語知識(文字、語彙、文法)読解、聴解を測るものであって、会話能力はあまり求められません。
そのため日本語を「読む」「聞く」はできても、話すのが苦手な方は一定数いるといわれています。
雇用した外国人に対して、定期的に日本語教室を開くなどのサポートを行うことが必要となるかもしれません。
2.就労できる在留資格を本当に持ってる?
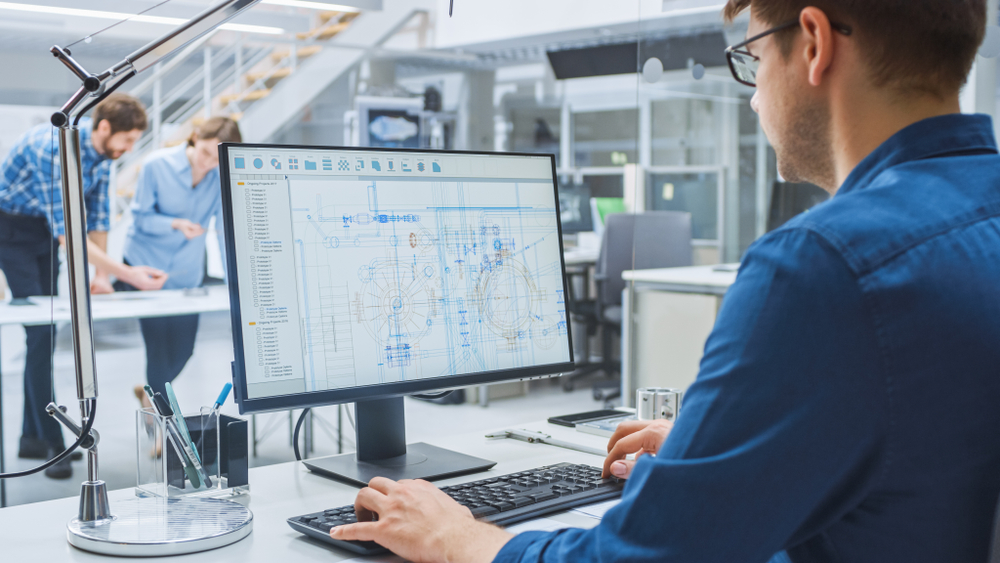
外国人が日本で就職するには、その業界で働くのに適した在留資格を持っている必要があります。
- 職種、業種を問わず就労できる在留資格(就労制限がない)
- 一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限って可能な在留資格
もし仮に「就労不可」の在留資格を持った外国人を雇用すると、法律違反となって場合によっては逮捕されてしまいます。
外国人を採用する際は、就労可能な在留資格を持っているのか確認しましょう。
基本的には在留カードの表面に就労の可否が記載されているので、チェックするのは難しくはありません。
ただし在留カードの有効期限が切れている場合や、ごくごく稀に偽の在留カードという場合もあるので注意しましょう。
なお、就労可能な在留資格は以下になります。
◇ 一の表(就労資格)
外交:外国政府の大使などとしての外交活動。またその家族としての活動
公用:外国政府の大使館、領事館の職員や、その家族などとしての活動
教授:大学などの機関における、研究や研究指導といった活動
芸術:作曲家や作家、画家などの芸術上の活動
宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道:外国の報道機関の記者、カメラマン
◇ 二の表(就労資格、上陸許可基準の適用あり)
高度専門職1号・2号:高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野
経営・管理:企業などの経営者、管理者など
法律・会計業務:弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行う活動
医療:医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこと
研究:政府関係機関、企業などの研究者としての活動
教育:小・中学校、高校での語学教師などの活動
技術・人文知識・国際業務(技人国):大学などで学んだ知識、母国の企業で培った経験などと関連する活動(単純労働は含まない)
企業内転勤:外国の事業所から、日本にある支店、本店などへの転勤者
介護:介護福祉士の資格を有する者が、介護または介護の指導に従事する活動
興行:演劇、演芸、スポーツなどの興行にかかる活動、または
技能:産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(外国料理の調理師、スポーツ指導者など)
特定技能1号・2号:
1号 → 特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識または経験の必要な業務に従事する活動
2号 → 特定産業分野(11分野:介護を除く)に属する熟練した技能が必要な業務
※2023年8月現時点
技能実習1号・2号・3号
特定活動の場合もあり
ただしスポーツ選手や外交官の家事使用人などに適用される「特定活動」というケースで、一時的に就労を認められる場合もあります。
一般企業で「特定活動」の外国人を受け入れるケースは極めて少ないため、詳しい説明は省きます。
資格外活動の場合もあり
また留学生は原則として就労が不可となりますが、「資格外活動」としてアルバイトが可能です。
在留カードの裏面の資格外活動許可欄に
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
と書かれている場合はアルバイトができます。
書かれていない場合は就労不可となりますので、入国管理局で資格外活動許可申請を行う必要があります。
3.雇用契約書を理解できてない?
作成した雇用契約書の内容を理解できておらず、後からトラブルになるケースも少なくありません。
外国人を雇用する際には、雇用する外国人の母国語でドキュメントを作成し、重要事項を確認したうえで、契約することが必要です。
もしくはひらがなベースでの日本語による記載や、英語が堪能な場合には英語の契約書を準備してもいいでしょう。
4.ブラックな職場で起きる失踪
こちらの資料「技能実習生の失踪者数の推移(平成25年〜令和4年上半期)」によると、平成25年から、令和3年(2021年)までは年間で平均で6,362名が失踪しています。
このような異常な状況を変えるべく、現在は技能実習生制度の見直しが進んでいます。
焦点としては、技能実習生にとって不利な状況を是正することでしょう。
雇用するのが外国人だとしても、日本人と同じように福利厚生を充実させることが非常に重要です。
5.就労中に訴えられるケース
外国人の就労中に訴えられるケースもあります。
例えば、解雇した外国人から訴えられる、残業代の未払いで訴えられる、セクハラ被害で訴えられる、外国人差別で訴えられるなどでとなります。
外国人を雇用する際は日本人と同様、「公正に労働環境を与え、妥当な賃金を支払う」義務があります。
外国人と日本人で待遇を分けるのはやめましょう。
また、面接や契約時にしっかりと労働環境や報酬面などを伝えたうえで、雇用する外国人しっかりと相互理解ができていれば、訴えられるようなことはないので安心してください。
外国人雇用でのトラブルを知って未然に防ぎましょう!
2023年1月末時点で、日本国内の外国人労働者は1,822,725人で過去最高を更新しています。
人材不足を補うためにも、国内企業は外国人を雇用する必要があるでしょう。
とはいえ外国人を雇用している企業が、いくつかの困りごとを抱えているのも事実です。
今回紹介したことを覚えておいて、実際の外国人雇用にぜひ役立ててもらえればと思います。