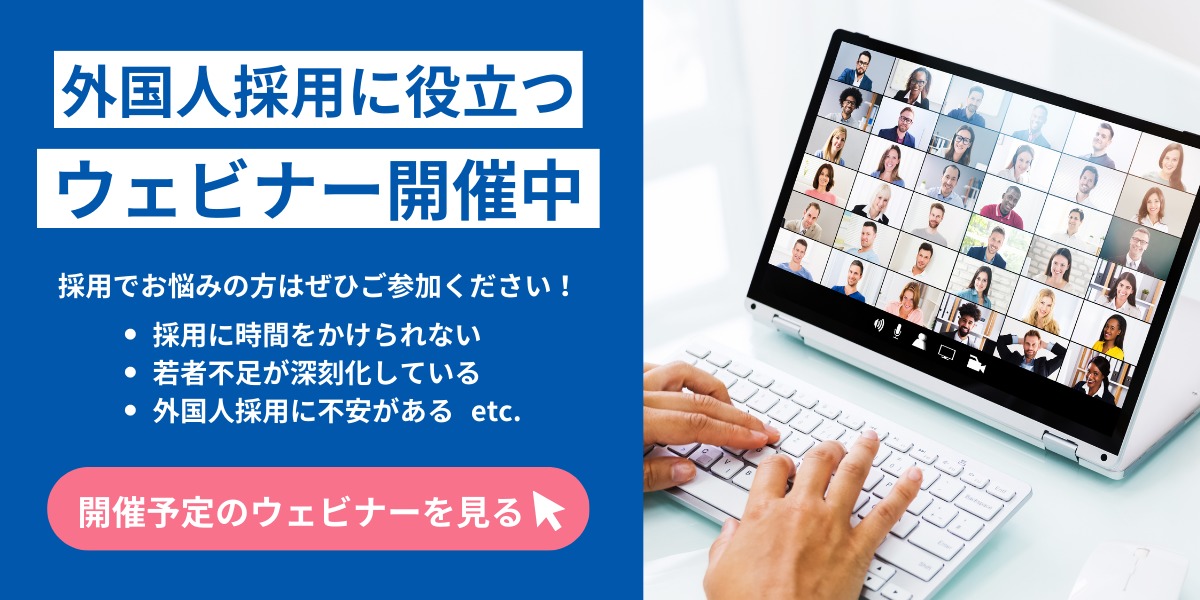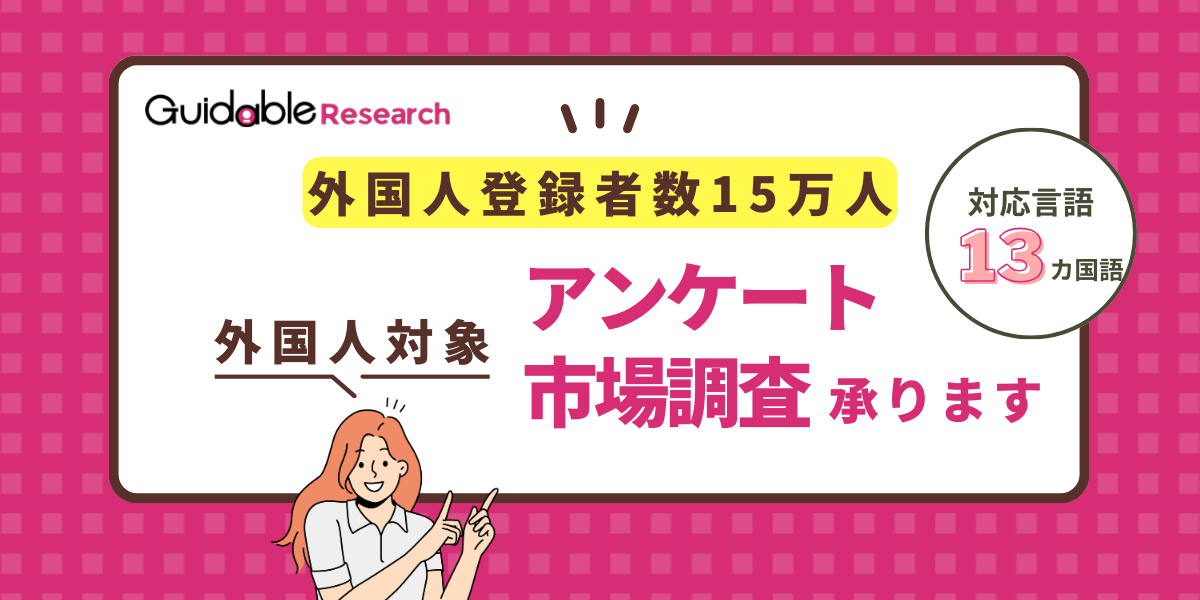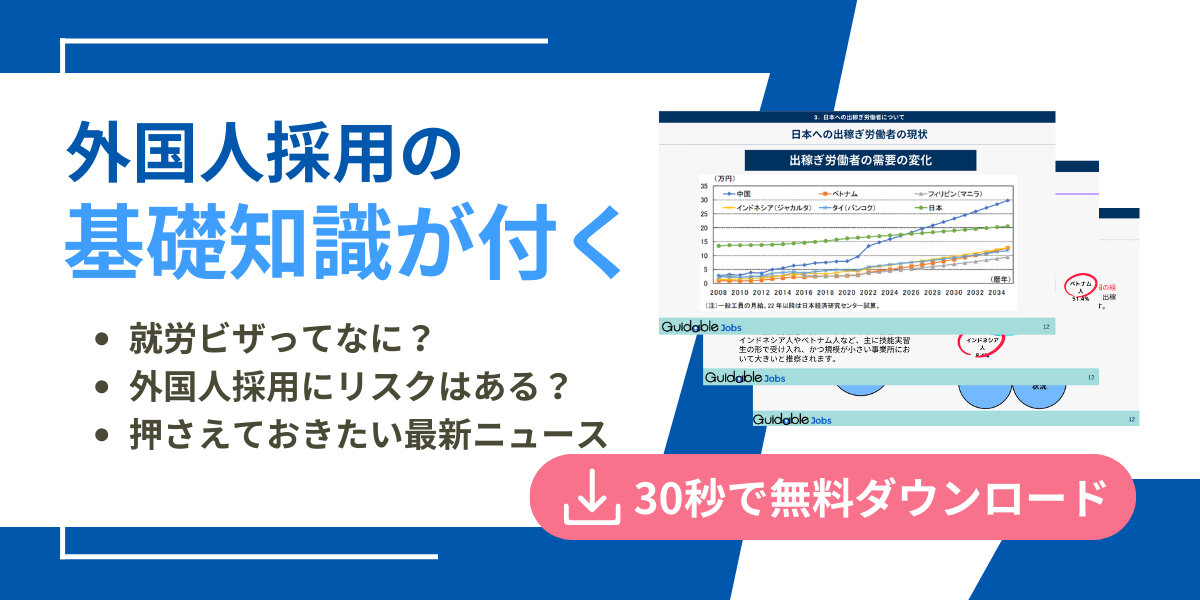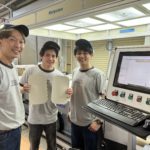外国人の医療費負担はどうなっている? 医療費の未払いが病院の経営を圧迫しているってほんと?!

訪日外国人の増加が著しい現在、受け入れ態勢や制度の面ではまだまだ整っていない現状があります。
そのために多くの問題が引き起こされており、とくに外国人医療費未払い問題が深刻化しています。
外国人を雇用している方や、外国人の友人がいるという方の中には、「治療費はどうすればいいんだろう?」「保険は入れるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は日本における外国人医療制度の現状や問題について、外国人が事前に知っておくべきことをご紹介いたします。
目次
【外国人医療費】どういう制度?

外国人医療費の制度はまだまだ整備されておらず、さまざまな問題を引き起こしています。大きな問題のひとつが外国人患者による医療費の未払い問題。
日本の多くの医療機関が経験している深刻な問題です。
では外国人医療費は、どのような制度になっているのでしょうか?
外国人医療制度の現状や未払い問題について、また医療費概算の事前提示とは何かについて詳しくご紹介いたします。
外国人に対する医療制度の現状
訪日外国人に対する医療費の価格設定は、それぞれの医療機関によって異なります。
医療機関が各々経営の方針や外国人を診察・治療するのに必要なコストなどを考慮し、各院で訪日外国人の治療費を決定しているのが現状です。
つまり医療機関によって価格が高かったり、低かったりします。
日本の医療機関において、医療サービスの価格は医療報酬制度に基いた「定められた価格」であるため、これまでは訪日外国人が支払う価格は日本人が払う価格と同等の価格でした。
しかし積極的に外国人患者の受け入れを行っている医療機関では、外国人患者への医療サービスは国民皆保険制度に該当しないとし、自由診療扱いにしているところもあります。
その場合、日本人の価格に対して一定比率を増した価格で受け入れをおこなっています。
このように日本の外国人の対する医療制度は整備されておらず、各医療機関によって異なるのが現状です。
医療費未払いの問題とは?

近年では外国人の医療費未払い問題が深刻化しています。
医療機関の約2割が経験しており、2019年3月末時点では総額で9,300万円、ひとつの医療機関で最大1,422万円もの外国人による医療費未払いが起こっていることが発覚しました。
産科と新生児科の両方が組み合わさった出産前後の母子に高度な医療サービスを提供する「周産期母子医療センター」によると、平成29年で10センターが訪日外国人の分娩を経験。
そのうち1センター当たりの1~3件において医療費未払いとなっており、中には130万円を超えるケースも発生していました。
医療費未払いは該当外国人が出国してしまうと徴収が難しくなるため、病院の経営を圧迫しかねません。
医療費未払いの約59%が在留外国人であり、調査以降、未払いの外国人に対する再入国拒否や、旅行保険の加入の催促など、外国人医療費未払いに対する対策が強化されました。
また「日本語がわからない」や「自分の加入している保険で使いやすい病院がわからない」といったコミュニケーション不足や、医療機関の説明不足も医療費未払いの原因として挙げられています。
留学ビザを使った医療費の「タダ乗り」問題
日本では、3ヶ月以上の滞在をする在留資格を持つ外国人は国民健康保険に加入する義務があります。
しかし、これを逆手にとって医療目的を隠し留学ビザを取得して来日し、医療保険を使って日本で治療を受けるというケースがあるようです。
たとえば留学ビザで日本に入国し、すぐに持病の治療を受けるといった事例も見受けられます。
留学ビザは申請書類が揃っていれば誰でも取得することができます。
医療目的を隠していたとしても、その真偽を審査するのは難しいのが現状です。
医療費概算の事前提示とは?
外国人の受け入れを行っている海外の医療機関では、通常の治療を行った場合のおおよそ掛かる医療費を即座に算出して、治療をするか否かの決断を促しています。
また患者側も初回の治療を受ける際に掛かる、おおよその費用を知りたい方が少なくありません。
そのため最初に治療に掛かる概算費用を確認してから、具体的な医療情報を提示する傾向にあります。
しかし医療情報が揃っていない中で、概算費用を算出することは容易ではなく、算出できたとしても正確性が低くなってしまうのです。
そこで国際医療交流コーディネーターが、医療機関からおおよその医療費を把握、それに加え医師と相談のうえ、合併症などの追加項目も把握しました。
通常の概算費用と合併症などの追加費用を足した概算費用の2パターンを事前提示することで多くの外国人に理解を得ています。
【外国人医療費】トラブルを避けるためには?
外国人患者の受入れには、言語がわからないことでコミュニケーションが取れず、誤った認識によってトラブルが起きてしまうなど問題が尽きません。
では、トラブルを避けるにはどうしたらよいでしょうか? 外国人患者受け入れ医療機関とはなにか? ご紹介いたします。
在留資格には注意!
訪日外国人の場合「短期滞在」もしくは「特別活動(医療滞在)」のどちらかの在留資格で滞在しているケースがあります。
それぞれ滞在期間や家族や親戚の同伴の可否が異なるため、該当外国人が入院・治療のための長期滞在は可能かどうかを確認することが必要です。
「短期滞在」には観光やスポーツ、親族への訪問、講習などが該当し、一般的には90日以内の滞在期間が許可されています。
さらに同伴者の同席ができません。
そのため長期的な治療が必要な場合は、滞在期間に合った治療計画の作成や親族への連絡などを念頭に置いておく必要があります。
一方で「特定活動(医療滞在)」は、診察や治療を目的として最大で6ヶ月の滞在、親族の同伴、数回の出入国が可能です。
短期滞在ビザの外国人患者の滞在が90日を超える場合は、医療機関の職員か日本にいる親族に近くの地方出入国在留管理官署から在留資格認定証明書を受け取る必要があります。
上記のように、在留資格によって滞在期間やその他の条件がまったく異なるため、長期の治療や入院が必要な場合は在留資格をあらかじめ確認することが必要です。
外国人患者受入れ医療機関とは?

訪日外国人が増えている中、各医療機関とともに地域における外国人患者の受入れ体制が整備がされています。
訪日外国人に適切な治療を安心して受けてもらえるよう、厚生労働省は外国人患者受入れ医療機関認証制度を策定。
多言語や文化、宗教などに対応可能な医療機関をリスト化しました。
外国人受入れ医療機関には選定基準が設けられており、その基準を確認し状況に応じた最適なリストに振りわけられます。
まずは都道府県ごとの「重症例を受け入れ可能な医療機関」を1カ所以上選出、つぎに外国人観光客が多い2次医療圏の「軽傷例の受け入れ可能な医療機関」を選出します。
外国人患者受入れ医療機関制度は患者の利便性高め、医療機関や行政サービスの向上を目的としており、外国人の受入れ体制は現在も整備が進められているのです。
外国人が知っておくといいこと
外国人が日本で治療する際にまず知っておかなければいけないことは、日本の国民健康保険や旅行保険に加入していない場合、日本の医療保険制度に基づいて各医療機関で設定された医療費を支払わなければいけない点です。
日本の国民健康保険や旅行保険に加入していない場合、自由診療となり外国人患者が全額負担しなければいけません。
自国で医療保険に加入しており、保険会社に医療費の請求をする場合、英文の診断書の作成を病院に依頼する必要があります。
英文の診断書の作成料金は病院によって異なるため、事前に確認するといいでしょう。
また、外国人医療費未払いのケースでよくあるのが、海外旅行保険未加入のまま日本での旅行中に病気やケガをし、膨大な医療費が掛かってしまうケースです。
医療機関としては、患者が「治療費は払えない・払わない」と診察前から明言しているなど、特別な事情がない限りは治療行為を行わなければいけません。
たとえ旅行保険に加入しておらず支払い能力がないとしても、放置することで患者の生命・健康に関わることが明らかだった場合には、医師は治療を行わなければ医業の停止・免許の取り消し処分を受けてしまいます。
短期滞在の方なら、もしものため旅行保険の加入をかならず行うことが大切です。
また3ヶ月を超える滞在の場合は、国民健康保険への加入が可能です。
外国人の医療費について、詳しくなりましたか?

在留外国人や旅行客が増えている日本。
それに伴って、外国人の医療費未払い問題が深刻になっています。
医療費の制度はあまり整理されておらず各医療機関によって異なりますが、外国人患者の受入れ体制は強化されました。
外国人医療機関がリスト化され、症状や地域を選択することで受け入れ可能な医療機関をすぐに検索することができます。
また、医療費概算の算出や外国語の対応も可能な医療機関も増えており、安心して滞在できる環境は今後ますます整備されることでしょう。
しかし外国人にも事前の対策が必要です。
しっかりと旅行保険や国民健康保険に加入して、もしもの場合に備える必要があります。
日本の医療制度の更なる整備、在留外国人の事前準備が外国人医療費未払い問題の改善につながっていくのではないでしょうか。
初めての外国人採用ならGuidable Jobsがおすすめ
人手不足の際にはさまざまな求人媒体をみると思いますが、外国人採用に特化した求人媒体があるのはご存じですか?
- 求人募集を出しても若い人が応募してこない
- そもそも求人に応募がこない
- 外国人採用を始めてみたい
採用を強化したい、と感じている方の多くがどんどん外国人採用を始めています。
少しだけ興味を持っている、という方でもぜひお気軽にご連絡ください。
国内には多くの永住者の方がいて、日本語も流暢に話すことができますが、まだまだいい条件で働ける場所が少ないです! すぐに人が欲しい! という方にこそ知ってほしい情報を共有させていただきます。